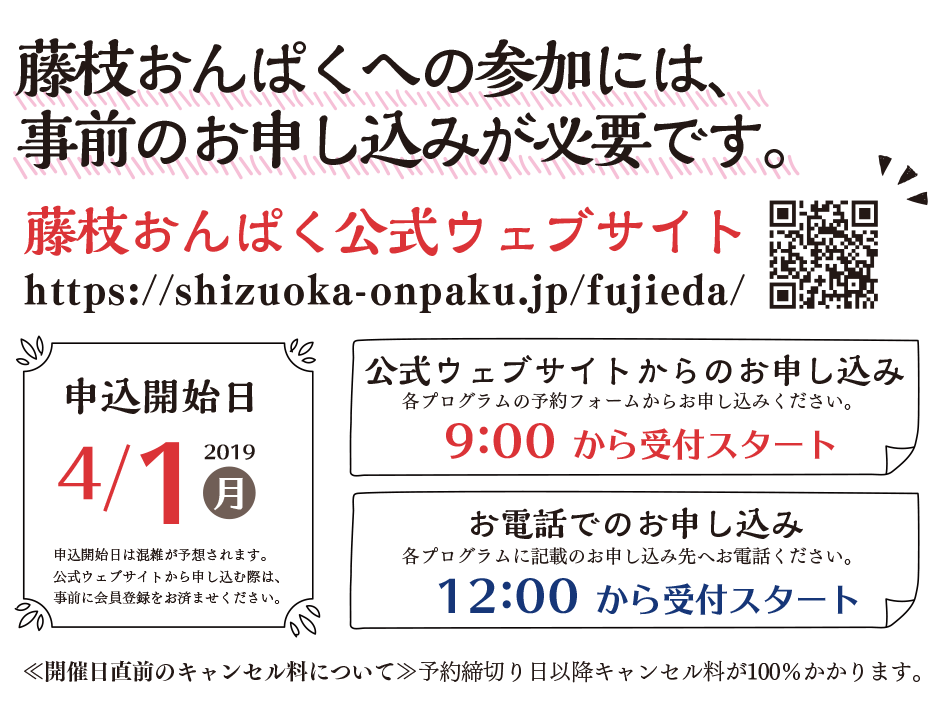「毎日食べる米を自分で育てたい」という方対象の講座です。
農薬・化学肥料を使わずに合鴨農法での米作りを共に働きながら農家から直接学ぶ全6回のプログラムです。
将来的に自分で田んぼを管理し、米作りをするための技術と知識を身に付けるため、作業の暦や技術、水管理、トラクターや除草機など機械の使い方まで、一緒に実際の作業を通して学びます。将来はマイ田んぼを目指します。午前は農作業の実践、午後には講座の時間。農村で有機農業が可能となる生物多様性や生命の循環、農村の暮らしや知恵など日々の暮らしと結びついた学びの場でもあります。
【1日の大まかな流れ】
(時間は作業の内容により、変わることがあります)
9:00 集合・作業開始
12:00 昼食(ご飯と味噌汁はこちらで用意します。おかずは一品持ち寄りでシェア)
13:30 講座(作業の振り返りとトピック)
16:00 終了
【全6回プログラム日程】
①4月14日
代かき(トラクターの使い方) + 合鴨農法の基礎講座
②6月2日
井上げ(川から田んぼへ水を引こう!) + 講座「オフグリッドな農村の暮らし」
③6月9日
田植え(手植えと機械植え) + 交流会
④8月4日
除草(田んぼの中と畦周り・除草機の使い方) + 講座「有機農業とは」
⑤10月27日
稲刈り(手刈りと機械収穫・ハサ掛け) + 講座(内容未定)
⑥11月9日
脱穀と籾摺り(脱穀機の使い方・天日乾燥) + 総括
【参加条件】
基本的に全日程に参加可能な方。将来的に自分の米を無農薬で作りたいという意欲のある方。(止むを得ず欠席の場合は作業内容によっては後日補習も可)
【参加費】
15,000円(1回2,500円× 6回)
【プログラム実施への想い】
藤枝市北部の瀬戸谷地域は山々に囲まれた静かな山村です。昔から山の上ではお茶が作られ、山間の限られた平地では米や野菜が作られてきました。四季を通して様々な作物が作られ、地域特有の農業や伝統文化が継承されてきました。
当地域は川の上流域にあるため、田んぼには清流からの綺麗な水が直接流れ込み、田植えの時期には蛍が舞い立ちます。夏にはツバメが、秋には無数のトンボが田んぼの上を飛び回ります。移り行く季節の中に田んぼがあり、様々な虫や鳥や動物たちが行き交い、私たちの暮らしがあります。
近年、農家の高齢化と過疎化が進み、山里からは人が消え、荒れた田畑が目立つようになってきました。田畑が荒れるということは、ただ単に耕作地が放棄され荒れるというだけでなく、その地域特有の技術、知識、伝統、文化が継承されることなく失われるということです。荒れた田畑は数年かければ元に戻りますが、一度失われた文化などは取り戻すことは極めて困難です。
あまりに急速に過疎化と農家の高齢化が進む中で、農村とそこに根付く特有の文化、技術、知識などを守り伝えていく人が必要です。これまでは農家の後継者がその担い手でしたが、その絶対数が少ないのです。意欲のある人が地域に入り、共に協力しながら地域を守っていくコミュニティ形成の一歩となればと願います。
田んぼプロジェクトでは米作りの技術だけでなく、人の手から手へと守り伝えられていく地域の豊かさも繋いでいきたいと考えています。
【主催と協力】
主催は「ちぃっとらっつ農舎」の杵塚歩と「ポラーノ農園」の鷲野浩之です。
協力は「瀬戸谷のめぐみ茶園」の箕作めぐみです。
県外出身の彼女は研修の後、昨年から同地域で独立しお茶づくりを始めています。
午後の講座では外部からの有識者を講師として招待することも計画しています。
小さい農園が協力しプログラムを構成していきます。プログラムを通して、参加者とも協働のあり方を探っていき、今後の地域内での協働体制の構築を目指します。小さい規模では機械や道具の所有、効率などハードルが高いように考えられがちですが、協力することでこれらの課題を解決していきながら、小さい規模だから実現できるクオリティや多様性などを大切にしていきます。
案内人

ポラーノ農園・鷲野浩之
多様性、地域、持続可能、伝統の手仕事、子どもの未来を大切に農を通して繋がり、繋ぐ
集合場所
注意事項
申し込み・問い合わせ先
☎090-8188-0808(きねづか)